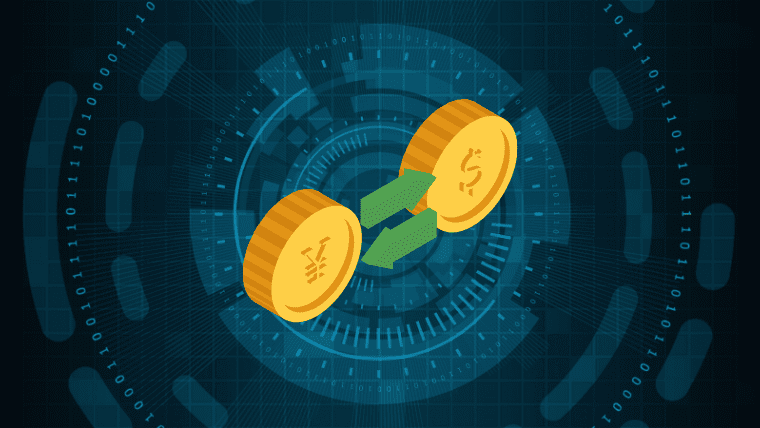SMC アルゴリズムの基本3原則をシンプルにまとめる

これまでLiquidity・FVG・Premium/Discountといった各概念ごとの切り口で1記事ずつ解説してきて、
「これがアルゴリズムの原則の1つです」が各記事に散らばっていて分かりにくいか...と思ったので、
「つまりアルゴリズムとは基本的にこの3つの原則に従う」という、概念を横断してまとめた切り口からの解説を1つの記事としてまとめておきます。
各概念の具体的な定義の話から離れて少し抽象的な話の集まりに感じるかもですが、
ICTが唱えるSMCでは「アルゴリズム脳」でチャートを眺めることがスタート地点からの第一歩です。
Liquidity・FVG・Premium/Discountの各記事の知識が一つの線につながることを目指して書いてみます。
基本原則として、以下2点をまず最初に覚えると良い
- アルゴリズムは、Liquidityを取りに行く
- アルゴリズムは、FVG(等の不均衡)を埋めに行く
この2点を覚えた後に、以下原則を付け加えるようにして覚えると良い
- アルゴリズムは、Premiumでショートを積みDiscountでロングを積む
この「2点 + 1」を覚えよう

ちなみに:
この3点は、SMC初学者向けのICTの動画「ICT Mentorship 2022 >>」を全て通して見て「つまり初学者が最初におさえると分かりやすいアルゴリズムのキモ・要点はこれだよな」と本記事筆者である"ぼくの主観"で抽出した要素になります。
「アルゴリズム3つの原則」という1つの動画がICTによってまとめられているわけではない、ということです。
その点は受け入れた上でお読みください。
他にも「アルゴリズムはこういうルールに従う」という決まりはあるので「他にもある、抜けてるじゃん」と感じてもここはスルーでお願いします。
(それが細かく分かる人はもはや初学者ではないのでこの記事を読む必要がない)
本記事は、Liquidity・FVG・Premium/Discountの各概念の解説記事をすでに読んでいることを前提に書いています。
各記事を読んでから読むことを推奨。
(本記事を読んでから各記事を読む...というのもアリかも?)
また、スマホではチャート画像が見にくいため、PCからアクセス・閲覧を推奨
ー もくじ ー
価格を動かすのは、アルゴリズム
ICTは、
Interbank Price Delivery Algorithm(IPDA/イプダ)というアルゴリズム(=AIプログラム=自動売買ソフトウェア)によって、全ての値動きが操作されている
...という前提でSMCの理論を構成しています。
SMCという概念を用いて分析する以上、
それって本当なの?
本当にそんなプログラムがあるの?
と疑う余地はありません。
太陽が東からのぼることを日常で誰も疑うことはないのと同じレベルで「値動きはアルゴリズムに完全支配されている」という前提を無条件に受け入れます。
アルゴリズムは"決まった仕事"の集まり
アルゴリズムは、エンジニアの手によって書かれたコードです。
コードと言われてピンと来ない場合、↓こんな感じの「プログラミング」の結果出来上がったソフトウェアと思ってください。

※ イメージです
このようにプログラムされたアルゴリズムが"全て"の値動きを支配するので、
▼一見ランダムに見える値動きに「解読可能な規則性を与える」ということです。

・・・このあたりで、本記事冒頭で書いた「アルゴリズム脳でチャートを見るのが最初の一歩」と言った意味・メリットが分かりはじめるのではないでしょうか。
- アルゴリズムには「あーしなさい、こーしなさい」という仕事内容・ルールが定められており、その通りに価格を操作している
- 逆に言えば、原則に沿わない仕事はしない
このように"価格を動かすのは全てアルゴリズム説"を受け入れることで、
アルゴリズムの決まりに従うだけでよい
アルゴリズムの決まりにないものは無視してよい
...というシンプルな考え方が可能になる。
まずはアルゴリズムの基本原則・ルールを理解することが重要。
...ということになります。
ちなみに:
アルゴリズムの決まりを定義して世に公開したのがICT(中の人はマイケル・J・ハドルストン氏)です。
つまり「アルゴリズムの決まり=ICTの定義」なので、ICTの定義を正しく理解することが「根拠ある分析」につながります。
アルゴリズムの基本原則2つ + 1
基本原則として、以下2点をまず最初に覚える。
- アルゴリズムは、Liquidityを取りに行く
- アルゴリズムは、FVG(等の不均衡)を埋めに行く
この2点を覚えた後に、以下原則を付け加えるようにして覚えると良い。
- アルゴリズムは、Premiumでショートを積みDiscountでロングを積む
イメージは↓こんな感じです。

▲覚える段階のイメージ
「3つ」というより、「2 + 1」というふうに考えた方が、文字通りピースがハマる感覚があるかなと(実体験)。
いきなりPremium/Discountまで含めて3つを同時に考えると、何が何だか分からない...となりやすい。
何よりもまず、LiquidityとFVGが最重要です。
以下、この2点 + 1について順番に書いていきます。
なぜ、価格は上下に動くのか?
この質問に対してICTが出す回答は、
アルゴリズムがLiquidityを取りに行くから
アルゴリズムがFVG(不均衡)を埋めに行くから
この2つだけである。
これ以外に価格が動く理由は存在しない。
...とシンプルに完結します。
▼ICTの動画から引用
ICT Mentorship 2022 Episode 12
アルゴリズムは、ハーモニックパターンやエリオット波動、(世間一般的な)サポレジラインなど見ていない。
それらは価格を動かす要素になり得ない。
トレンドラインや移動平均線も同様だ。
アルゴリズムが見ているのは、FVG(不均衡)の均衡とLiquidity。
これだけだ。
ーーー以下原文ーーー
Smart Money traders(=Algorithms), someone that's not looking at a chart with harmonic ideas, nothing Elliot Wave, they don't even look at support and resistance.
That's not a factor at all.
They care less about trend line. They don't care about moving averages crossing over.
They are looking at imbalance rebalance, and liquidity.
That is it. That's all they're doing.
原則1:Liquidityを取りに行くから価格が動く
これが、まず最初に頭に叩き込むべき基本中の基本中の基本です。
Liquidityを追いかけ回すのは"アルゴリズムの本能"と理解してください。

アルゴリズムはLiquidityを追い求めるよう作られている
▼具体例
▼ドル円週足、歴史的160円台到達したところから、140円台へ下落したところ。

月足から1秒足まで、全ての足で同じように考えられます。
▼ゴールド5分足のチャート例(別にゴールドである必要はない)

Liquidityを取ったらまた別のLiquidityを取りに行く、これの繰り返し
▼この原則から分かること
▼なんか伸びてるな?と思ったら、その方向にLiquidityがある=アルゴリズムがターゲットに設定しているのかもしれません。

その方向が上ならBias=Bullish、下ならBias=Bearishということ。
▼伸びている方向にあるLiquidityに逆らってショートをするよりも...

▼伸びている方向にあるLiquidityに向かってロングをする方が、成功可能性が高い。

原則2:FVG(不均衡)を埋めに行くから価格が動く
アルゴリズムはLiquidityを取りに行く
という原則に、
アルゴリズムはFVG(不均衡)を埋めに行く(だから価格が動く)
という原則もつなげます。第二の本能です。

▲なぜ価格は下がっていったのか?の理由が「FVGを埋める仕事をするため」です。
▲なぜ埋め終わった後に上がっていったのか?の理由が「FVGを埋める仕事を終えて、Buy side Liquidityを取りに行く仕事を始めたから」です。
「FVGが残っていたら埋めろ」とプログラムされたアルゴリズムは、埋めに行かざるをえない
▼ドル円 月足
勢いよくSell side Liquidityを取りに行った後にできたFVGを埋めに行くアルゴリズム

▲なぜ価格は上がっていったのか?の理由が「Sell side Liquidityを取る仕事を終え、FVGを埋めにいく仕事を始めたから」です。
▼Bullishな時は、不均衡を均衡しに下がっていく→FVGがサポートになり上昇

▼Bearishな時は、不均衡を均衡しに上がっていく→FVGがレジスタンスになり下落

▼これら原則から分かること
まずシンプルにFVG単体で考えると、
▼なんか伸びてるな?と思ったら、その方向にまだ埋まっていないFVGがある=アルゴリズムがターゲットに設定しているのかもしれません。

▼上記同じチャートを4時間足で見た図

その方向が上ならBias=Bullish、下ならBias=Bearishということ。
▼ゴールド日足、Bullishの例

1分足〜1時間足など短期足のみ見ていると、月足・週足・日足など上位足FVGを見逃しがちになります。
上位足ほど下位足に与える影響が大きいので、上位足FVGを見逃す=致命的な分析ミスを引き起こすことに...。
月足・週足・日足のFVGのチェックは忘れないように要注意。
FVG単体だけでなく、
Liquidityを追い求める + FVGを追い求める
この2つの原則を組み合わせると、色々なことが考えられるようになります。
▼Liquidityだけでなく近接するFVGがある場合、アルゴリズムは「一石二鳥」を目指して、FVG単体、Liquidity単体で存在する場合よりもそこへ向かう可能性が高いかも?

Liquidityを取る + FVGを埋める
▼上記チャートの続き・Bullishな状況と仮定
ロングの損を確定させBullish FVGを埋めたので、FVGがサポートとして機能→buy sideにあるFVG埋め・もしくはLiquidityを狙いに行くかも?

Liquidityを取る + FVGを埋める
▼ゴールド日足を見てみると、上記と似たような例が確認できます。

Liquidityを取る + FVGを埋める
アルゴリズムはLiquidityを取りに行きFVGを埋めに行く、だから価格が動く
...というのは「アルゴリズム脳」で考えるための基本
▼不均衡の種類
これは本記事で初めて書くことです。
FVG以外にも「不均衡=埋める対象」とみなされるモノがある点は把握しておきます。
- Volume Imbalance / ボリューム インバランス
- Liquidity Void / リクイディティ ボイド
▼Volume Imbalanceは、連続する"2本"のローソク足で実体続きにならずヒゲ交差している部分。

▼Liquidity Voidは、一般的な"窓"で、連続する"2本"のローソク足でbuyもsellもない部分

※ Liquidity Voidは、2016年のICTの動画を見ると定義が異なっており、新しい動画ではこのように解説している点に注意
それ以外に価格が動く理由はない
▼"需要と供給"は無関係
需要が多い=買いがたくさん入れば価格が上がり、供給が多い=売りがたくさん入れば価格が下がる
これをICTは否定します。
アルゴリズムの「Buy Program(買いプログラム)」が起動すれば、
売りボリュームがいくら入ってこようともBuy sideにあるFVG・Liquidityへ向かって上がっていく
アルゴリズムの「Sell Program(売りプログラム)」が起動すれば、
買いボリュームがいくら入ってこようともSell sideにあるFVG・Liquidityへ向かって下がっていく
...と考えます。
▼ICTの動画から引用
2022 ICT Mentorship Episode 16
買い圧力・売り圧力というものは、作り話だ。
(Bullishの例を見ながら)市場価格は、入ってくる注文量に関係なく上昇する。
アルゴリズムがこのbuy side liquidityへ向かって上昇したいのなら、大量の注文は必要ない。
ーーー以下原文ーーー
The buying and selling pressure, it's a myth.
Because these markets are gonna go higher regardless of how many contracts come in.
If they(=Algorithms) want this thing to go up here, it doesn't require millions of contracts to put it there.
よって、ICTは以下のような注文量・ボリュームに関わる情報を無価値だと考えます。
- 板読み(Depth of Market/DoM)
- TradingViewなどで利用できる「出来高プロファイル/ボリュームプロファイル」
- フットプリントチャート
ちなみに:
ICTがSupply/Demandを否定する理由、Supply/DemandでSMCを解説されることにブチギレている理由が、
このとおり「アルゴリズムにとってSupplyもDemandも関係ないから」です。
▼その他、色々無関係
ワイコフ理論でSpringイベントが待っているから下落するのではなく、
エリオット波動で第5波が待っているから上昇するのでもなく、
三尊・逆三尊の形が出来たから下落・上昇をするのでもなく、
ダウ理論で上昇トレンドと定義される事象が確認できたから上昇するのでもありません。
移動平均線・ピボット・RSI・ボリンジャーバンド等この世に存在する全てのインジケーターで自動表示されるラインも、アルゴリズムは何も認識しません。
繰り返しますが、
▼上下にLiquidity・FVGがあり、それをアルゴリズムが追い求めるから価格は動きます。

原則3:Premiumでショートを積みDiscountでロングを積む
次に、この原則を組み合わせることで「なぜアルゴリズムがそのような値動きをするのか」の理解度が飛躍的に向上します。
まず、以下復習としてPremium/Discountの基本的な定義を思い出してください。
▼Premiumでショートを積む
アルゴリズムは、高すぎる価格帯=売り得なPremiumでショートを積む(ロングの利確も行う)

▼Discountでロングを積む
アルゴリズムは、安すぎる価格帯=買い得なDiscountでロングを積む(ショート利確も行う)

・・・
さて、ここから本題です。
何度か例として出してきた、ドル円月足をもう一度見てみます。
▼LiquidityとFVGだけで考えた場合
Sell side Liquidityを取ったので、Buy sideに残るFVGを埋めに行った...という理解ができます。

▲これだけでも「なるほどね、アルゴリズムの原則通りだね」と納得できますが...
▼Premium/Discountを加えた場合
Premium/Discountを明確にすることで、
アルゴリズムは(Liquidityを取りながら)Discountでロングを蓄積したということが可視化される
↓
だから高値で売るためにPremiumを目指す
という根拠が加わることになり「"FVGを埋めるという仕事"を果たしに上昇する」と考える妥当性が強まります。

▼Liquidityを取っただけでなく、Discountでじわじわとロングを積み上げてPremium FVGへ向けて上昇準備をしているイメージを養います。
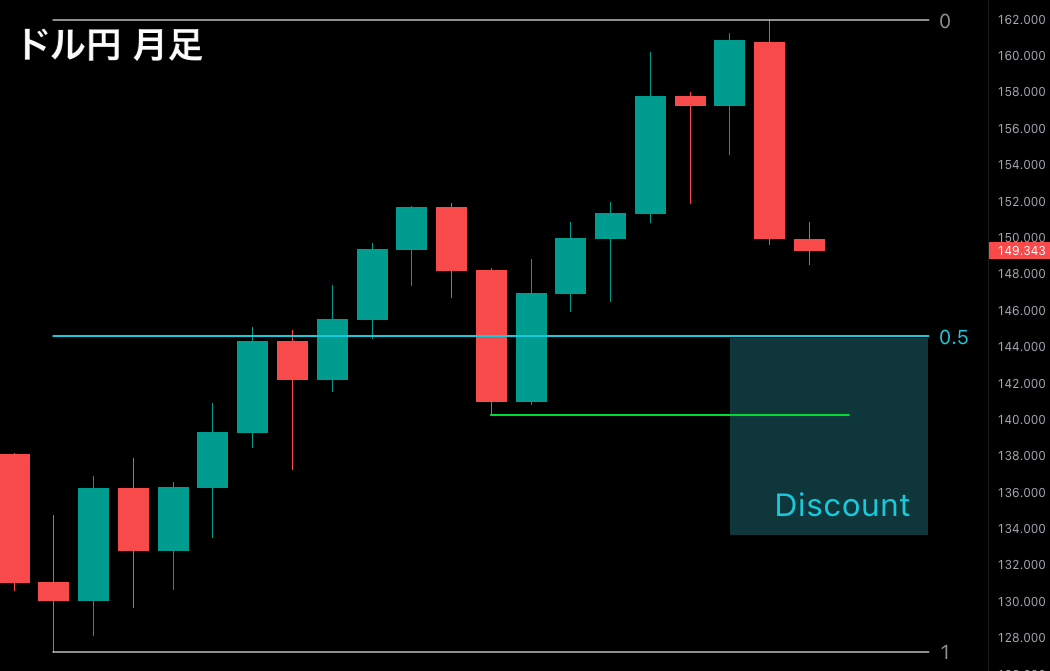
▼もし、月足チャートを見て、Discountにいる時点でこのような分析ができていたと仮定すると、Premiumへ向かうまでの値幅で"アルゴリズム的視点から十分な根拠のあるロング"が狙えたことになります。

▼アルゴリズムの原則3点を、もういちど整理

▼「Premiumで高く売る」と書きましたが、ではそこからまた暴落を始めるかというとそうとも限らず、Bullishと仮定した場合はPremiumを突き抜けてBuy side Liquidityを取りに行く可能性もある点は考慮します。

▲Discountで積んだロングを、より高値で利確するため"Liquidityを取りに行く"というアルゴリズムの原則と矛盾しません。
▼逆にBearishと仮定した場合、Premiumでショートを積んだアルゴリズムが安く買い戻して利益を出すためにDiscountのSell side Liquidityを目指す可能性もあります。

▲これもPremiumで積んだショートを、より安値で利確するため"Liquidityを取りに行く"というアルゴリズムの原則と矛盾しません。
・・・
もう一つ、これもすでに例として出したゴールド日足。
▼LiquidityとFVGだけで考えた場合
Premium/Discountを抜きで考えると...

▲ロングを狩ってFVGを埋めたからと言って、それだけではBuy side Liquidityへ向けて一直線に上昇する根拠が薄いように感じます。
▼Premium/Discountを加えた場合
Discountエリアを明確化しただけで、ロングを狩り取ってFVGを埋めただけでなく、
▼上昇へ備え"Discountでロングを積み上げる"というアルゴリズムの意図が可視化される

ロケットに燃料を注ぎ込むように上昇の準備としてDiscountでロングを積み上げているのが分かるので、Discountから離れた後にBuy side Liquidityへ向かって一直線に上昇するのも納得できるのではないでしょうか。
▼ICTの動画から引用
ICT Mentorship 2022 Episode 16
アルゴリズムはDiscountからPremium・PremiumからDiscountへと動いていく...というロジックの中で、アルゴリズムはLiquidityを取りに行くか、FVGを生成/均衡する。
わかった?
これがアルゴリズムの動作の全てだ。
ーーー以下原文ーーー
It(Algorithm) seeks Discount to Premium, Premium to Discount.
Within that logic, the market is reaching for liquidity in the form of buy stops and sell stops, and OR, the creation of imbalances(≒FVG) or returning back to FVG.
Okay?
That's all these algorithms do.
・・・
ここまでの「アルゴリズム基本三原則」を踏まえたうえで、もう一度以下Premium/Discountの解説記事の「実際に引いてみよう」の章に載せたチャート例を復習してみてください。
参考ICT Premium/Discountの基礎:実際に引いてみよう
まとめ:「一石三鳥」をイメージする
「アルゴリズム基本原則2 + 1」の総仕上げに入ります。
ここまで月足〜日足など上位足のみの例が多かったので、下位足まで含めた解説をします。
(全ての時間足で同じ考え方が適用できるということです)
まず、順番に状況を整理していきます。
▼ドル円月足でこのFVGを半分埋めたところ

▼日足で拡大すると、月足FVGを半埋めした後に日足の⭐️FVGが生成されたところ(2024/10/24(木)がクローズ時点)。

▼さらに15分足で拡大したところ

▼直下にSell side Liquidity・日足FVGが控えた15分足、という認識で読み進めてください。

・・・状況確認はここまで・・・
▼少し時間を進めると、ここで日足FVGを埋めにいくと見せかけて、ギリギリで埋めませんでした。

▼ここで、このSell side Liquidityは「Equal Low」と考えます。

▲つまり、単一Liquidityよりもさらに吸引力が強いEqual Lowと吸引力の強い上位足(日足)FVGが残ったままの状況(Bias=Bearish)であることが最重要ポイントとまず理解してください。
ここで、アルゴリズムの原則をもう一度思い出します。
アルゴリズムのターゲットが下にあるとき、
- Buy side Liquidity(ショート損切り)を取ってからターゲットへ下落
→ 一般トレーダーがショートで簡単に利益を出すのは許さない
→ 一般トレーダーに「上昇か!?」と勘違いさせる - FVG(不均衡)を埋めてから下落
- Premiumでショートを積んでから下落
→ トレンドを勘違いさせた後に「本当の動き」を見せる
ということを意図的に実行します。
この↑ポイントをおさえた上で、順番に「アルゴリズムが見ているモノ」を表示していきます。
▼1:Buy side Liquidityがある

▼2:Liquidityの直上にFVGがある
=ここにしか残ってない「不自然な」FVG

このFVGに無意識レベルで目が行くかどうか
▼3:PremiumにLiquidity・FVGが重なる

▼Premium FVGを埋めに行くことで
アルゴリズムの基本原則3つを全て同時に満たせる「一石三鳥」になります。

▼ジェットコースターの坂を登り、下落の準備体制が整ったアルゴリズムはあとは重力(という名のEqual Low & 日足FVG)に吸引されるままに下落。

▼つまり、
価格はアルゴリズムによって100%操作される
↓
アルゴリズムは決められたプログラムにしたがう
↓
プログラムを解釈できたら、アルゴリズムに乗っかりショートを狙っていく

▼最後に、一連の流れをもう一度確認。

▼注意すべきこと
この例で忘れてはいけないのは、下にあるターゲットが明らか、つまり少なくともターゲットに至るまでのBiasがBearishであることが明らかだった、という点です。
▼たとえば同じチャートでも、仮に先にSell side Liquidityを取り日足FVGを埋めていたとしたら、BiasはBearishとは言い切れず、Premium FVGでショートをするのが適切なのかどうかは熟考すべきでした。

「Buy side Liquidityを取りつつPremium FVGを埋めたら即ショート」という単純な話ではない点だけご注意を。
▼時間足は関係ない
15分足の例で見ましたが、1分足でも(秒足だとしても)考え方は全く同じです。
#ゴールド 1分足で拡大
1. Equal Lowを取りつつdiscountへ
2. わずかな埋め残しFVGを埋める
3のFVGがラストチャンス https://t.co/8zsiAyXu3h pic.twitter.com/r74KjEv17r— Yuki📈|ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) September 16, 2024
総復習
アルゴリズムのターゲットが上にあるとき、
- Sell side Liquidity(ロング損切り)を取ってからターゲットへ上昇
→ 一般トレーダーがロングで簡単に利益を出すのは許さない
→ 一般トレーダーに「下落か!?」と勘違いさせる - FVG(不均衡)を埋めてから上昇
- Discountでロングを積んでから上昇
→ トレンドを勘違いさせた後に「本当の動き」を見せる
ということを意図的に実行する
...というアルゴリズムの3つ(2+1)の原則を再度ふまえた上で、
▼「Bullishの状況」と仮定し、この後のアルゴリズムに都合の良い展開(=すでにロングを保持する一般トレーダーにとって都合の悪い展開)を考えてみてください。

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・
・・・・
・・

・・・
以上、アルゴリズムの基本原則2 + 1でした。
いきなりリアルタイムチャートを見て「この先アルゴリズムは何を意図するのか?」を読むのはハードルが高すぎる(それができたら誰でも簡単に稼げる)ので、
すでに確定した過去ローソク足を見て、Liquidity・FVG・Premium/Discountを都合よく引き、
確かにLiquidityを取りに行っている
確かにFVGを埋めに行っている
確かにPremiumで売りDiscountで買っている
というそれぞれの概念に対する経験を伴う実感を得ながら、
Liquidityを取る
+
FVGを埋める
+
Premium/Discountに重なる
=これが上手く重なると確かに"明確な意図"を持って価格が動いているように見える
...という経験を伴う実感を得ていくことで「アルゴリズム脳」が育つかと思います。
#ゴールド 5分足 SMC
確定したデータからアルゴリズムの意図を解釈する練習を積む👀
1. sell side liquidity取る(ロング狩る)
2. FVG埋める
3. discountでロング積む
↓
buy side liquidity & FVGへ https://t.co/kUbmDRmaf1 pic.twitter.com/P5qJF7w3kw— Yuki📈|ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) October 28, 2024
ローソク足しか見てないのに...
マジでアルゴリズムが意図を持って動かしているようにしか見えなくなってきた。
スゴすぎでは?面白すぎでは?
...と思えるようになると良いですね。
▼目と脳のトレーニング用に再度まとめ



▼参考ポスト
SMC アルゴリズムの原則:
1. liquidityを取りに行く
2. FVG(不均衡)を埋めに行く
3. premiumでショートを積み、discountでロングを積むこの3つの基本原則全てを簡潔に表している動きだね https://t.co/6L5Pl2FYUg
— Yuki📈|ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) September 13, 2024
#ゴールド 15分足 SMC
equal lowを取りdiscount FVGを埋めた
↓
equal highを取りpremium FVGへ・FVGを埋めに行く
・liquidityを取りに行く
アルゴリズムがする仕事はこのどちらかのみ
(正確には"FVG"限定ではなく"不均衡") https://t.co/R6WKf6AfFg pic.twitter.com/zpWzZkenGD— Yuki📈|ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) October 7, 2024
#ゴールド 15分足 SMC
「アルゴリズムはLiquidityを取りにいく or FVG(不均衡)を埋めに行く、このどちらかだけ」の原則より、
今朝起きた時点でこのequal lowと日足FVGが怪しい...と思えたら正解だった例😮 pic.twitter.com/cvRihfELSj— Yuki📈|ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) October 15, 2024
#ゴールド 15分足 SMC
・FVG埋める
・premiumでショートを積む
・sell side liquidity(pdLow)を取りにいく
...というアルゴリズムの意図が見えるのでは👀
premium + FVGに重なってるOBの精度にも注目 pic.twitter.com/Khk4xcDSXZ— Yuki📈|ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) October 25, 2024
本記事で解説した3原則を根幹としたシンプルな分析例を、以下記事で載せているので参考にしてください。